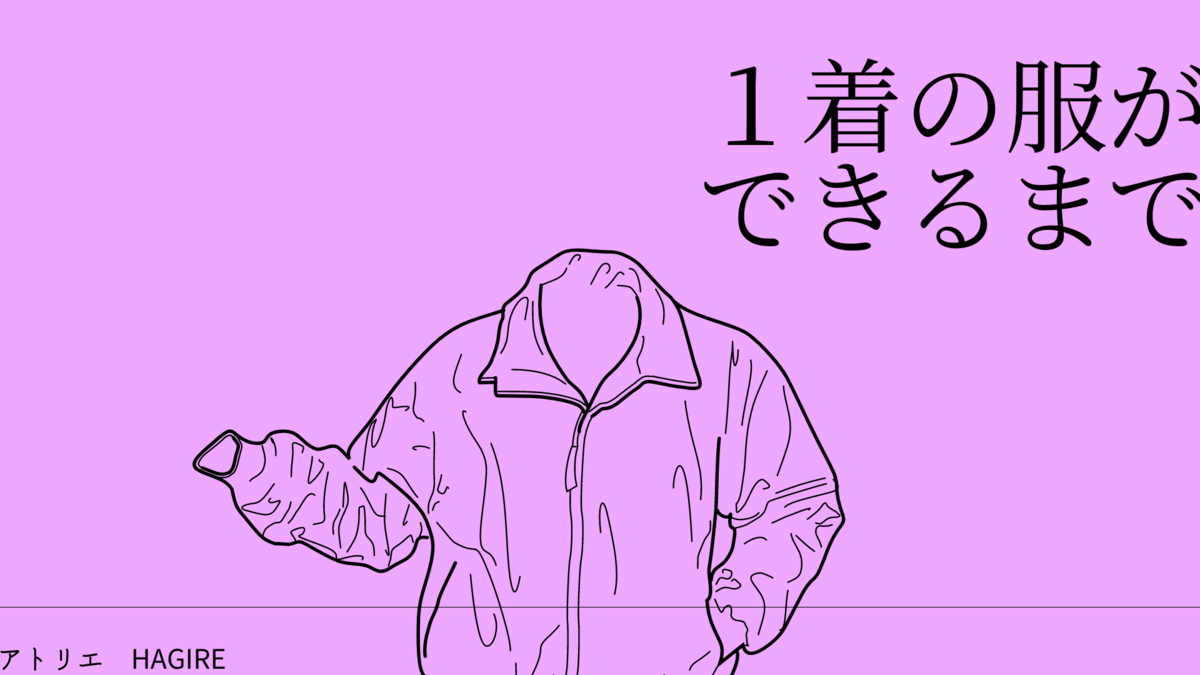
洋裁をひとりで学んでいると、1着の服をつくるためにはいろんな作業があるんだなあ、という発見が毎度のようにある。
自分で型紙をつくりたいと思って、洋裁CADをいじってみたり、ミシンが壊れたから修理してみたり、かがり縫いのためにロックミシンの練習をしたり。
ひとりで楽しむ洋裁アトリエだったら、こうゆういろんな作業を断続的に、好き勝手やっていくことができるけれど、
工場生産で服をつくる場合は、たくさんのひとが製造の工程に関わるだろうから、あっちやこっち、みたいなやり方ではないのだろうなあーと考えた。
それで、工場生産の服が、どのようなプロセスでつくられているのかを調べてみました。
服の工場生産に関わるすべての人々


StylisteとModeliste

服作りの最初の最初の着想はSTYLISTE(服飾デザイナー)
が描くデザイン画からはじまる。
STYLISTE(服飾デザイナー)
は、いろんなデザイン画を、ラインナップにして、
MODELISTE(型をつくるひと)
と共有する。
STYLISTE(服飾デザイナー)とMODELISTE(型をつくるひと)
は、デザイン画をたたき台にしながら、
デザイン面や、技術面などの視点でお互いのアイデアを共有していく。
そのようにして、着想段階のデザイン画を具体化していく。
トワルをつくる

デザイン画が具体的になり、さて、次は実際に布で組み立てて形をみてみよう、ということになる。
そこでMODELISTE(型をつくるひと)が試作品としてトワルをつくる。
このトワルをつくるひとは、TOILISTE(トワルをつくるひと)
と呼ばれることもあるそう。
パターンをつくる

TOILISTE(トワルをつくるひと)がつくったトワルを、ベースのサイズとし、そのトワルを平面製図するのが
MODELISTE PATRONNIERE (パタンナー)
MODELISTE PATRONNIERE (パタンナー)は、工場生産用のパターン
を製図するひとなので、デザインや技術面で工場生産が可能となるように、STYLISTE(服飾デザイナー)
MODELISTE(型をつくるひと)
と話し合ってデザインを調整しながら、パターンを製図する。
パターンが出来上がったら、
モデル(型)を縫製するひとが、実際の布をつかって、
パターン通りに縫製する。
サイズ展開をするパタンナー

縫製が終わり、パターンが決まると、ベースのサイズからサイズを展開していく。
PATRONNIERE GRADEUSE
はベースサイズで引かれた平面製図を、異なるサイズに展開していく。
MODELISTE PATRONNIERE (パタンナー)
とPATRONNIERE GRADEUSE
は、サイズ展開の際にデザインが崩れないかなどをチェックしながら、展開されたパターンとベースのパターンを共有する。
最初の工場生産

サイズ展開されたパターンを、はじめて工場で生産する段階。
モデル(型)を縫製するひと
が実際の布をつかって、すべてのサイズの縫製を行う。
MODELISTE PATRONNIERE (パタンナー)
とPATRONNIERE GRADEUSE
は、出来上がったすべてのサイズの試作品を確認する。
STYLISTE(服飾デザイナー)
MODELISTE(型をつくるひと)
と共有してきた、デザインやディテールが、試作品のそれと、合致しているか。
パターンの数値と出来上がりの数値に誤差はないか。
サイズ展開によるデザインや外観の崩れがないか。など。
最後にパターンを調整し、試作品で再び確認後、サイズ展開された工場生産用のパターンの完成になる。
製造の手順と製造業務

パターンから服を作り上げるための
地直し、型紙を布にうつす、裁断、パーツを組み立てる、縫製、などの様々な作業を具体的に指示するための内容を作成する。
工場のキャパシティーと、製造環境(どのような機械がそろっているかなど)を考慮しながら、生産の工程をわかりやすく具体的に工場に伝える必要がある。
生産と品質チェック

製造の手順と製造業務の内容が作成され、それをもとに生産のリーダーが工場のメンバーと一緒に現場で製造する。
最後に完成した服を、点検し、オーケーがでたものが、出荷される。
参考資料
ESMOD Méthode de gradation
イラスト画像と編集